福岡 北九州 下関 沖縄 頼れるプロの便利屋ハンズクラフト・ライフサポート!家具・家電・雑貨などの不用品回収、遺品整理・生前整理・ハチ駆除など、あらゆるお困りごとに対応いたします。
福岡 北九州 下関 沖縄 頼れるプロの便利屋ハンズクラフト・ライフサポート!家具・家電・雑貨などの不用品回収、遺品整理・生前整理・ハチ駆除など、あらゆるお困りごとに対応いたします。
ブログ一覧
CASE
2025.03.12
遺品整理とは、故人が生前に使用していた 私物や家族のために残した遺産などを整理することです。
遺品整理の最中に故人との思い出がよみがえり、寂しさを感じる場合もありますが、遺品を綺麗に仕分けることで気持ちを整理できるメリットがあります。
遺品整理を行う時期に正解はないので、基本的には家族や親族の気持ちが落ち着いてから行っても問題ありません。
ただし、亡くなった後に行わなければならない手続きがいくつかあり、期限を守らないとトラブルにつながる場合があるので注意が必要です。
ということで今回は、遺品整理のベストなタイミングや時期、いつから始めるべきか目安などについて解説していきます。
何から始めるべきかについてもご紹介しますので、ぜひ最後まで読んで参考にされてみてください。

まずは遺品整理を始めると安心なベストなタイミングや時期について解説します。
四十九日とは、故人が亡くなって49日目に行われる法要を指します。
仏教では故人が極楽浄土に入れるかの裁判は死後49日に渡り行われるとされており、この期間を目安に遺品整理が行われる場合も多いです。
四十九日には多くの親族が集まるため、このタイミングで遺品整理のスケジュールや進め方、形見分けなどについて納得いくまで相談し合えば、後々のトラブルを防げます。
遺族や相続人の了承を得ずに自己判断で遺品整理を進めると、必要なものまで処分してしまう恐れがあるので注意しましょう。
故人と同居していた遺族であれば、葬儀の翌日ぐらいから少しずつ遺品整理を開始してもよいでしょう。死亡届の提出や施設の退去期限(目安)は7日以内ですし、他にもやる事が出てくる可能性があるので、少しずつ進めるに越したことはありません。
ただ、繰り返しになりますが、他の遺族がいる場合に了承を得ないまま自己判断で進めようとするとトラブルに発展しかねません。
本格的に遺品整理を行うのは、あくまでも四十九日に遺族が集まって今後のことをしっかり話し合ってからがおすすめです。
葬儀の翌日ぐらいから少しずつ遺品整理を進めるにしても、遺品の整理整頓や仕分け、貴重品を探す程度にとどめましょう。
人が亡くなった直後は、役所への死亡届けの提出をはじめ、遺族が協力し合い様々な手続きを進めなくてはなりません。
中でも健康保険証の返還などの社会保険関係、電気・ガス・水道の解約、年金の受給停止、クレジットカードの利用停止は必須といえます。
そのため、親族や相続人が集まりづらい場合や故人が賃貸物件に住んでいた場合は、解約手続きが完了したタイミングで遺品整理を行うケースが多いです。
「亡くなって14日後〜」を目安にしていますが、支払い期限が近いものや受給日が定められている場合など、重要なものからできる限り早めに対応するようにしましょう。
たとえば、ご親族が遠方に住んでいて集まりづらい場合や出来るだけ早い段階で遺言書や相続財産の内容を把握したい場合、故人が賃貸物件に住まわれていた場合などは、なるべく早い段階で遺品整理を始めると安心です。
たとえば、親族が遠方に住んでいる場合は中々集まれないことも多いと聞きますので、葬儀や告別式の合間をみて遺品整理や形見分けを進めるのが一般的です。
また、故人が賃貸物件に一人暮らしていた場合は、いつ次月の支払いがいつなのかの確認や管理会社等への連絡が必要となります。
こういったケースでは、所有物の整理だけではなく、関係各所への連絡や手続き等で追われてしまうため、少しでも早く遺品整理を始めるとトラブルも少なく、作業を終えることができます。
遺産が相続税の非課税額を超えた場合は、相続税の申告と納税が必要です。
その場合は、故人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があると定められています。
ですので、「そもそも相続税を支払う必要があるか」「いくら支払うか」を判断するには、故人が残した遺産の評価総額を求めなくてはなりません。
そのためにも、まずは遺品整理を行い、預貯金や不動産など何が相続税の対象になるか把握する必要があります。
ですので、相続税の申告を行う必要がある場合は、申告を行う少し前から遺品整理を始める方がトラブルが少ないとされています。
では、遺品整理に期限はあるのでしょうか。次の章では、遺品整理はいつまでに対応するべきなのか解説していきます。
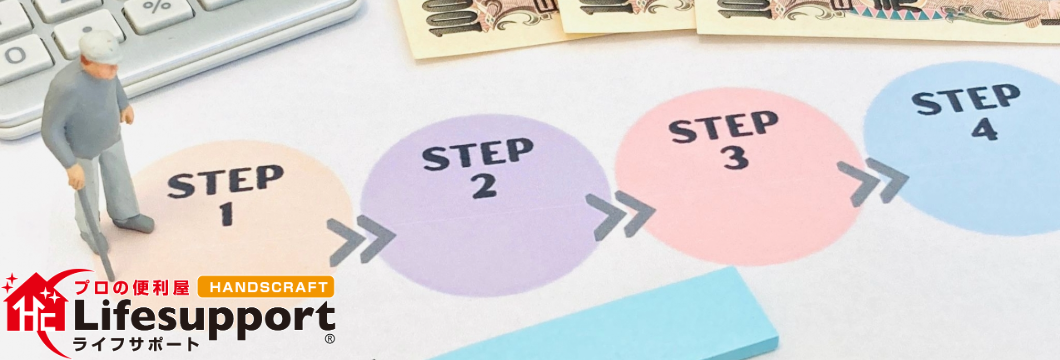
実は、遺品整理をいつまでに行うかどうかの決まりはありません。ただし、これから紹介するタイミングを考慮して進めないと、思わぬトラブルに発展したりする恐れがあるので注意が必要です。
相続税の申告期限は、故人が亡くなってから10ヶ月以内です。申告期限は他にも「自分が相続人であると知ってから」など色々な表現をされるので、判断がつかない場合は専門家に相談しましょう。
まずは申告期限までに遺産整理を行い、故人の財産や資産を正確に把握する必要があります。
相続は手続きも含めて非常に複雑です。
早めに遺品整理を進めることで税務上のトラブルを回避できる可能性が上がるので、10か月ギリギリではなく余裕を持って進める必要があります。
相続放棄とは、マイナスの遺産も含めて引き継がないようにする手続きです。相続放棄するかどうかの選択期限は、亡くなってから3ヶ月以内と決められています。
必要書類を揃えて家庭裁判所で手続きをすれば期間を延長できますが、弁護士など専門家への依頼が必要になるケースもあるので注意が必要です。
仮に故人が多くの借金をしている場合、相続放棄しないと相続人に返済義務が移るため大変です。
もしすぐに遺品整理を始められない場合でも、最低限、借金の有無を確認して相続するかどうかを決めておきましょう。相続放棄する場合は、事前に手続きの流れを確認し、必要書類も揃えておくとスムーズです。
基本的に賃料は月払いなので、賃貸契約書を確認して可能な限り来月分の賃料が発生する前までに遺品整理を開始しましょう。
固定資産税とは、土地や建物に対して課される税金のことです。
固定資産税は毎年1月1日の時点で、土地や建物を保有している人に対して課されます。つまり、12月31日~1月1日の1年間を対象にした課税ということになります。
例えば、1月2に新しい家を購入して同じ年の12月31日に古い家を手放したら、その年は固定資産税が課されません。要するに、1日1日の時点で土地や建物を保有しているかがポイントです。
したがって、遺品整理を開始するタイミングも、固定資産税が発生する前である1年以内が一つの目安となります。
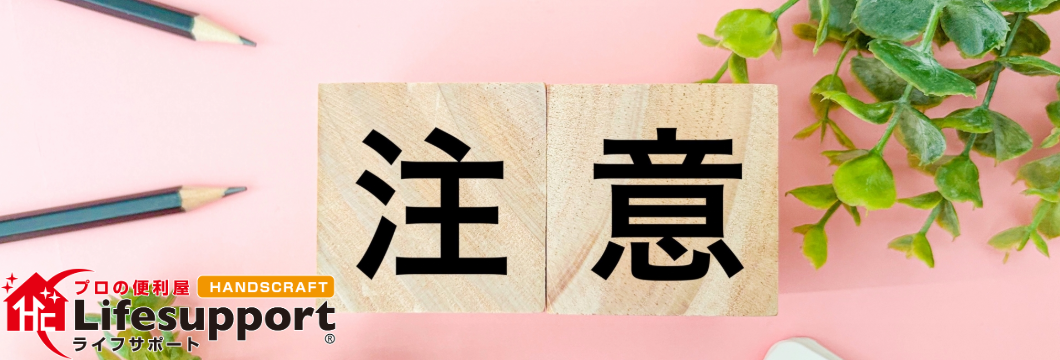
自分だけで遺品整理を進めるとなると、スムーズに進まないことも少なくありません。相続に関する知識が全くなかったり、手続き全般に不慣れであったりすれば尚更です。
ここでは遺品整理を進める際の注意点を紹介しますが、共通してできるだけ早く始めることを意識しましょう。
遺品整理はスケジュールが少しぐらい遅れても、遺族の気持ちが落ち着いた段階で始めるのが最適といえます。ただし、遺品整理が遅れることで周囲に迷惑がかかる可能性がある場合は、できるだけ急がなくてはなりません。
その一つの例が、故人が孤独死をしたケースです。遺体の発見が遅れた場合、悪臭や害虫の発生など周囲にまで被害が及ぶ可能性があります。
また、自分自身の不利益につながるリスクも考えて進めなくてはいけません。例えば、故人が借金していた場合やライフラインの解約を済ませていない場合は、できるだけ早く対応しないと自分の負担が大きくなってしまいます。
遺族の気持ちを優先することはもちろん大切ですが、周囲と自分自身への影響も考慮して、ベストなタイミングを見極めましょう。
故人が賃貸住まいだった場合、退去手続きをするまでは家賃が発生するので、なるべく早く遺品整理を開始するのがおすすめです。
まずは賃貸契約書を見つけ、契約内容を参考に遺品整理のスケジュールを立て、期日までに家賃を支払うようにしてください。故人が月の後半で亡くなった場合は無理に急ぐ必要はありませんが、できるだけ翌月の家賃が発生しないうちに進めましょう。
賃貸は一般的に原状回復を求められ、場合によっては高額のクリーニング代や補修費用を請求される場合もあります。また、故人が自分でエアコンなどの家電を設置していた場合は、取り外し工事や廃棄の費用も請求されるケースも出てきます。
賃貸に関してはお金と時間がかかるケースも多いので、大家や管理会社と連絡を取りながら、余裕のあるスケジュールで進めていきましょう。
倒壊のリスクや衛生上有害となるなど、放置することでトラブルを引き起こす可能性がある空き家を「特定空き家」といいます。
特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、納税額が跳ね上がってしまう場合があります。
また、特定空き家の調査後の「指導・助言・勧告」に従がわない場合は、50万円以下の過料が課される可能性があるので注意が必要です。
遺品整理は遺品だけに着目するのではなく、建物がどのような状態にあるのか家の中・外から細かく確認するようにしましょう。
建物に何かしら問題が見つかった場合、早めに対処するほど特定空き家に指定されるリスクが減ります。
相続税の申告は、故人が亡くなったことを知ってから10か月以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が課せられるので注意しましょう。
相続税の申告は株式や預貯金など遺産の総額を正確に把握することが第一歩です。また、故人の負債や葬祭費用など控除対象になるものも含めて、正確に計上しなければいけません。
このように、相続税の申告は専門的な知識も必要になり複雑といえます。万が一申告漏れがあると、追徴課税を課されて本来の納税額よりも多く支払わなければなりません。
自信がない場合や時間に余裕がなければ、税理士や弁護士など専門家の力を頼るのも安心です。
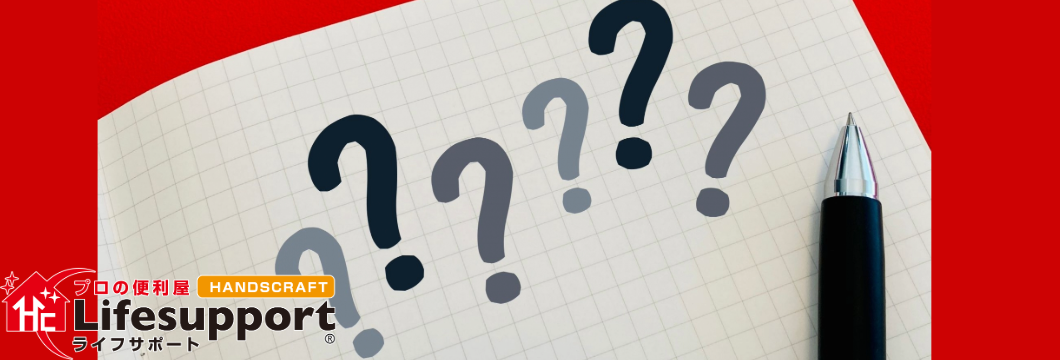
故人が一人暮らしだった場合、空き家の管理を怠ったり、遺品整理が遅れて長い間放置したりすると様々なトラブルが起こる恐れがあります。
ここでは、特に遺品や空き家を放置することによる代表的なトラブルと対処法を紹介していきます。
空き家の管理を怠るリスクとして、まず挙げられるのが火災トラブルです。
電気ケーブルや家電は劣化によって故障を引き起こすケースもあります。そのため、電気やガスを解約せず長く放置している場合、非常に危険な状態といえるでしょう。
また自然発火することもあるので、なるべく早く遺品整理を進めるとともに、空き家の状態を細めに確認するようにしてください。
他にも放火犯に狙われるなど、空き家を放置することによる火災リスクは大きいといえます。
ライフラインの解約や遺品整理が遅れる場合には、ブレーカーを落としたり資産価値のありそうなものを回収したりするなど、最低限の対策をしましょう。
空き家は特に老朽化が進みやすく、強風や地震だけでも倒壊するリスクがあります。今後住む予定がなくても、定期的に点検とメンテナンスを行い、通行人や周辺住民に迷惑がかからないようにしましょう。
既に手の施しようがないほど老朽化が進んでいるのであれば、解体するのも一つの選択肢です。
今回は、遺品整理のベストなタイミングや時期、いつから始めるべきか目安などについて解説していきました。
ここまで述べてきたように、空き家や遺品の管理は、火災や倒壊、盗難のリスクを減らす上で欠かせません。
空き家を解体しない場合や置き場所などの理由から遺品を空き家に一定期間残しておく場合は、遺品整理後も定期的に管理することが大切です。
また、遠方に住んでいるなど空き家の管理が難しくなる場合は、空き家管理サービスの利用を検討してみてください。
空き家管理サービスとは、主に空き家の管理を定期的に行うのが難しい所有者に代わり、空き家を管理するサービスを指します。
料金によってサービス内容は異なりますが、月に1回程度、空き家を訪問して清掃や郵便物の管理を行うのが一般的です。他には建物の点検や換気、雨漏りの点検などを代行してくれます。