福岡 北九州 下関 沖縄 頼れるプロの便利屋ハンズクラフト・ライフサポート!家具・家電・雑貨などの不用品回収、遺品整理・生前整理・ハチ駆除など、あらゆるお困りごとに対応いたします。
福岡 北九州 下関 沖縄 頼れるプロの便利屋ハンズクラフト・ライフサポート!家具・家電・雑貨などの不用品回収、遺品整理・生前整理・ハチ駆除など、あらゆるお困りごとに対応いたします。
ブログ一覧
CASE
2025.05.14
遺品整理の際には、誤って処分してしまうと大きなトラブルへと発展してしまうものがあります。
■勝手に処分するとトラブルになりやすいもの
上記一覧に挙げたものは、「法的」「トラブル防止」「手続き上」いずれかの理由で処分する際には慎重になる必要があるとされているものです。
これらの遺品を勝手に処分しまうと、遺品整理において必要な手続きができなくなるだけではなく、親族間の争いが起こるなど思いがけないトラブルに発展する恐れがあります。
ということで今回は、遺品整理の際に捨てるとトラブルになりやすいものについて解説していきたいと思います。

「法的」「トラブル防止」「手続き上」いずれかの理由で処分するのが望ましくないとされています。
ここでは、この3つの理由に分けて詳細を確認していきます。
遺言書には故人の遺志が記されており、何より法的な拘束力を持っています。
誤って捨て処分してしまうとトラブルに発展する可能性が高いので、遺品整理の際に遺言書は優先的に探すようにしましょう。
遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分けられます。
自筆証書遺言の保管方法は決まっていないので、自宅の金庫や鍵のある引き出しなどの場所から探してみてください。なお、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、管轄の法務局で保管されています。自宅で見つからない場合は問い合わせてみましょう。
「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は公証役場に保管されるので、有無を確認してみてください。
それでも遺言書が見つかなければ、生前親しかった知人や銀行に預けている可能性があるので、スマホや手帳などを手掛かりに探してみましょう。
以下のものは、適切に遺産分割を進めるために必要になります。
その他、ローン明細などマイナスの遺産を証明する書類も遺産分割において必要になるので、誤って処分しないようにしましょう。
現金は遺産分割の際に必要ですが、法的にも捨てることは禁止されているので注意しましょう。
具体的には「貨幣損傷等取締法」という法律があり、貨幣(現金)を故意に損傷させると「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
もちろん故意に行った場合なので、誤って処分したことが認められれば罪には問われません。ただ、故意でないことをどうやって証明するかということになるので、現金の扱いには注意しましょう。
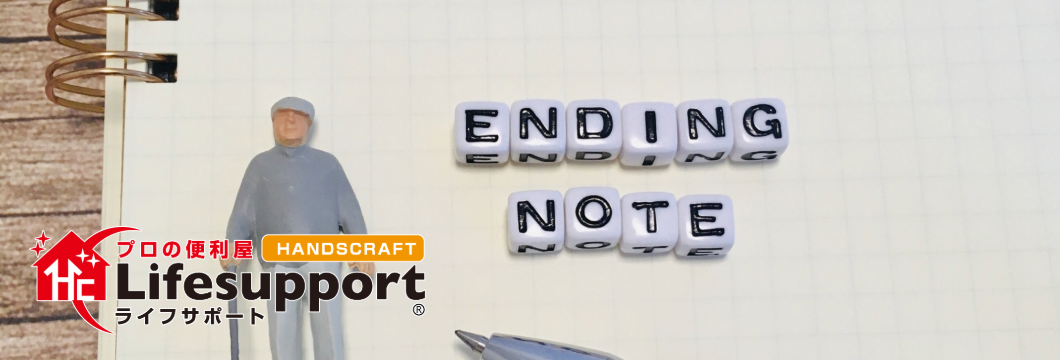
次に、法的には問題なくても処分するとトラブルにつながりやすいものについて解説していきます。
遺言書とは違い法的な効力はありませんが、故人の想いが記載されているので大切に保管しましょう。
近頃はパソコンやスマホにデジタル遺品として音声や動画を残すケースが増えています。
データは端末の色々な部分に保存されており、実物と比較して見逃しやすいので、隅々まで探すようにしましょう。
暗号資産など相続の対象になるデータが保存されている場合もあるので、スマホやパソコンは大切に保管しておきましょう。
レンタル品・リース品は、企業から貸与されているものです。
個人の所有物ではないので、誤って捨ててしまうと違約金や損害賠償を請求される恐れがあるので注意しましょう。
以下のものはレンタル品である可能性があるので、誤って捨てないように注意してください。
これらの他に、洋服もレンタルサービスを利用している可能性があるので注意しましょう。
レンタル品は大体の場合、提供元のステッカーが貼られているなど見分けられるようにしている場合がほとんどです。
生前に何をレンタルしているか聞けなかった場合は、遺品一つ一つをしっかり見てレンタル品かどうかを見極めましょう。
遺品整理中に鍵が出てきたら大切にとっておくようにしましょう。大切な資料や資産価値のあるものは、金庫や引き出しなどに施錠して保管されている場合が多いです。
鍵を誤って捨ててしまうと必要な手続きを行えなくなる恐れもあり、専用業者に解錠してもらう必要が出てきてしまいます。
性格が大雑把な方だと、洋服のポケットに入れっぱなしにしている可能性もゼロではありません。面倒かもしれませんが、遺品一つ一つを慎重に確認して本当に必要ないと思った時点で捨てるようにしましょう。
これらは相続の対象になるとともに、高値で売却できる可能性もあります。もし売却価値がありそうなものが見つかったら、他の遺品と分けて保管して、後日査定に出すようにしましょう。
自分で売却価値がありそうなものを見極める自信がなければ、遺品整理と同時に査定対応してくれる業者もあるので検討してみてください。
故人が生前に気に入っていたり思い入れがあったりして残したいものがないか、事前に確認しておくようにしましょう。
遺品整理を担当する人にとっては価値のないものにうつっても、故人や遺族にとっては大切な思い出である可能性もあります。
例えば手紙や洋服で色褪せてボロボロになっているものでも、大切にしていた可能性もあるので、自己判断で処分しないようにしましょう。
デジタル遺品とは、パソコンやスマホなどにデータとして保存された遺品のことです。写真や似顔絵などの思い出の品は、そのまま保管すると劣化が進んだり紛失したりする恐れがあるので、敢えてデータとして残している人もいます。
PCやスマホを処分する際は、内部に大切なデータが残っていないかどうか確認するようにしましょう。
また敢えてデジタル遺品として保管しているのは、プライバシー上、他人に気軽に見られたくない理由もあります。
そのため、前もって遺言書やエンディングノートなどで、デジタル遺品に関して指示がないか確認してから動いた方がよいでしょう。

次に手続き上、必要となるものについて解説していきます。
金融機関が故人の死を認識した時点で銀行口座は凍結します。
凍結した銀行口座を解除するには、通帳・キャッシュカードの他、遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本などが必要です。銀行によって必要書類は異なるので、前もって確認しておきましょう。
そもそも、通帳やキャッシュカードを紛失すると、遺族や正式な相続人でも現金を引き出すのが難しくなるので注意してください。
逆に通帳があれば記帳内容から取引内容を確認できるので、例えばローンや加入保険の関連で、どの会社とやりとりがあったかを把握できるので便利です。
先に紹介した凍結口座の解除をはじめ、諸々の手続きには印鑑が必要です。役所に登録した実印でないとNGの手続きも多いので、印鑑登録証明書も探して大切に保管しておくようにしましょう。
また、印鑑登録は原則として一人一つまでですが、故人が経営者であった場合は会社の実印も所有しているはずです。
会社の代表として契約書に判を押す機会は頻繫にあります。いつでも対応できるようにスーツやカバンに印鑑を入れている可能性は十分に考えられるので、必ず確認しましょう。
故人が年金を受給している場合、年金手帳や年金証書は処分しないようにしましょう。死亡後10日(国民年金は14日)以内に※死亡届を年金事務所に届け出ないと、亡くなった後も年金が支給されてしまいます。
手続きには、年金手帳に記載されている情報が必要です。
※日本年金機構にマイナンバー登録している方は不要
死亡届が必要かどうか判断できない場合は、早めに日本年金機構に確認するようにしましょう。
参考文献: 「日本年金機構―年金受給者が亡くなった時の手続き」より
身分証明書は役所での手続きの他、故人が生前に契約していた各種サブスクリプションサービスを解約する際にも必要になります。
■身分証の一覧
近年では有益なサブスクリプションサービスが増えているので、故人がスマホやパソコン上で複数契約している可能性は高いです。
「どの端末で・どんなサービスに登録しているか」は故人しか知り得ません。
自己判断で解約手続きを進めると、もし見逃した有料サービスがあった場合は延々に料金が発生することになります。
解約する際は請求書や利用明細書を参考にして、全てのサービスを解約したか確認するようにしてください。
相続はマイナスの遺産も対象になります。例えばローンの残債が多い場合は相続放棄も一つの選択肢になりますが、手続きは相続発生から3ヶ月に行わなければいけません。
ローンの存在に後から気付いて慌てることがないように、ローン明細書は故人の自宅をくまなく探すようにしましょう。またローン会社に問い合わせて、正確にどれくらい残債があるのかも把握するようにしてください。
公共料金や税金関連の請求書・支払い通知書は、捨てずに保管してください。
例えば電気・水道などのライフラインは、解約しないと料金が発生し続けるので、捨ててしまうと未払いの料金を把握できず放置してしまうことになりかねません。
未払料金の支払い責任は相続人に引継がれるので、未対応の請求書が見つかったら速やかに支払いを済ませる必要があります。
また既に説明した通り、相続はマイナスの遺産も対象になるため、故人が借金をしている場合も相続放棄しない限り相続人が支払い責任を負うことになります。残債を一括請求される場合もあるので、請求書を処分してしまうと気付かないうちに利息が膨らんで大変なことになるでしょう。
仕事関連の資料の中には、会社の重要情報が含まれている可能性があるので捨てずに保管おきましょう。
一見仕事とは関係なさそう物品も、会社から貸与されたものである可能性もあります。
仕事関連のものは一か所にまとめて保管している場合が多いので、付近にあるものは念のため捨てない方がよいでしょう。
一通り遺品整理が終わったら、会社に連絡を取って返却するものがないか確認しましょう。
不要であれば、そのまま処分しても問題ありません。
土地も相続の対象ですが、権利書がなくても相続登記をはじめとした手続きは行えるので無理に探す必要はありません。
ただ、権利書があれば相続人間での話し合いがスムーズに進むことが多いので、故人名義の土地がある場合、権利書は捨てずに残しておきましょう。

遺品整理を行う際は、徹底した事前準備が大切になります。遺品整理は故人の所有物や家族との大切な思い出を扱うため、相続や遺族とのやりとりの中でトラブルが起こりやすいからです。
ここでは、遺品整理を自分で行う場合に最低限注意するポイントを紹介するので、内容を参考にしてみてください。
遺品整理は葬儀の後や四十九日法要後に開始するのが一般的です。他には、(相続放棄する場合)相続発生から3ヶ月以内、相続税の申告期限である10ヶ月以内を目安にしましょう。
具体的な遺品整理のスケージュールを立てたら、遺族に共有しましょう。
スケージュールについて「もっとこうしてほしい」など意見や要望をもらえる場合もありますし、時間が合えば遺品整理を手伝ってもらえる可能性もあります。
自己判断ではなく遺族としっかりコミュニケーションを取りながら遺品整理を進め、意見の食い違いや誤って捨ててはいけない遺品を処分してしまうリスクを防いでいきましょう。
遺品整理を始める前に作業手順とルールを明確にしておけば、不用なトラブルを軽減できスムーズに作業を進められます。
例えば、以下のようにマニュアルやチェックリストを作っておくのがおすすめです。
遺品の量が多い場合は、階や部屋ごとに作成するとよいでしょう。
まずは遺言書の有無を確認し、内容に沿って遺品整理を行うようにしましょう。遺言書は法的な効力があるので、内容に従わないと相続時のトラブルにつながる可能性があります。
遺言書は故人の遺志を示すものです。
仮に遺言書が正式なものでなければ、遺品をどのように扱うかを遺族の間で話し合うこともできますが、基本的には遺志を尊重する形にしましょう。
相続放棄とは相続時に発生する財産や負債を引き継がないことです。
相続放棄を実施するには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、「相続放棄申述受理通知書」を受け取ります。
手続きは故人の死後(相続発生から)3ヶ月以内に行う必要があるため、相続放棄をせずに遺品整理をはじめると相続する意思があると見なされる可能性があります。
マイナスの遺産が多く相続によって負担が増えることが想定される場合は、早急に遺族に対して相続放棄の意思を確認しましょう。

遺品が多すぎて自分だけで対応しきれない時は、遺品整理業者への依頼を検討しましょう。
豊富な知識と経験を持った遺品整理業者に依頼すれば、短時間で遺品整理が完了するのに加え、故人や遺族の心情に配慮した最適な方法で遺品の仕分けや処分を行ってくれます。
費用はかかりますが、自分で遺品整理を行うよりも体力・精神面ともに負担を大幅に減らせるのが魅力です。
ただし、悪徳業者も少なからず存在するので、依頼する際は以下を確認して信頼のある業者に依頼しましょう。
遺品整理業者は一般家庭から数多くの遺品を回収しますが、その際に必要になる資格が「一般廃棄物収集運搬許可証」です。
基本的に資格を保有している業者のみが、日常生活の中で出る不用品を回収できるので、業者に依頼する際は必ず確認するようにしてください。
一般廃棄物収集運搬許可証は市区町村が出しているので、ホームページなどで確認できない場合は直接問い合わせるとよいでしょう。
なお、許可を持っていない業者でも、一般廃棄物収集運搬許可証を持った業者に委託していれば問題ありません。
資格の有無を確認できない場合は、まず許可を持った委託先がないかを確認するとよいでしょう。
今回は、遺品整理の際に捨てるとトラブルになりやすいものについて解説していきました。
遺品整理を行う前に親族間で何を残すのかを話し合えば、大切な遺品が勝手に処分されたといったトラブルを回避できます。
遺品整理や相続の際にトラブルが起こるケースは想像している以上に多いです。前もって「いつ・誰が遺品整理を行うか」を決め、特に意見が分かれやすい「遺品の分配や処分範囲」については親族をはじめ相続と関係する人達と十分に話し合うことが大切です。
話し合いが難航する場合は、遺品整理相談窓口に相談してみるなど、専門家の意見を取り入れるのもおすすめで、プロの視点からのアドバイスを貰えます。